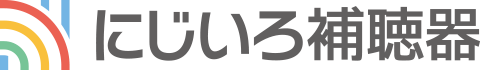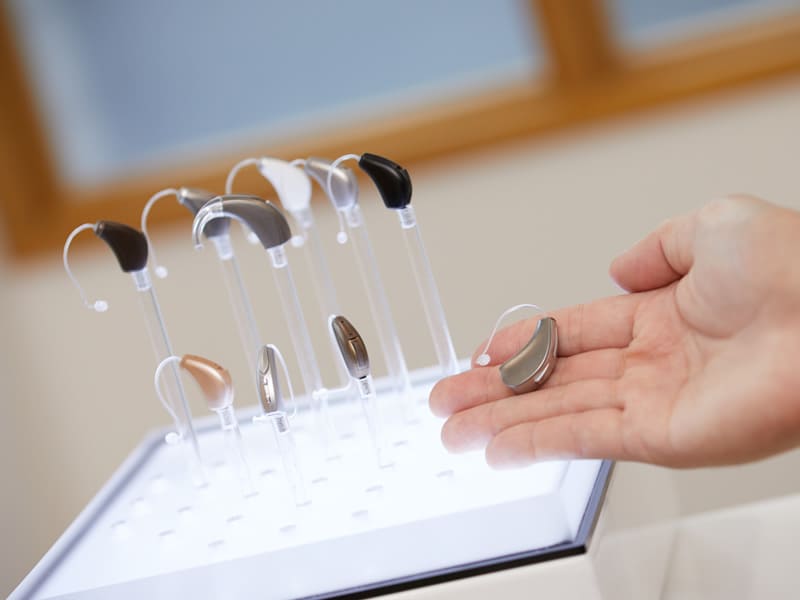補聴器・聞こえの
無料相談受付中
(予約優先制)
日常生活の音の種類


【監修】千葉 星雄
にじいろ補聴器 店長
言語聴覚士・認定補聴器技能者
「音とは?」と尋ねられたとき、イメージするものは何でしょうか。音楽や話しことばはもちろん、私たちは、多くの音に囲まれて生活をしています。
この記事では、私たちが触れている「音」について深めてみましょう。
話しことばも音のひとつ
話しことば(話し声:はなしごえ)は、人同士のコミュニケーションの中で最も便利なコミュニケーション手段です。
話し声も音から成っており、様々な周波数の音が含まれています。周波数の違いは簡単に言うと音の高さです。
高さの異なる音が組み合わさることによって、日本語であれば「あ」「い」「う」など、ひとつひとつの音が出来上がっています。
人間は人とのやりとりをしながら、自分以外の人のことばを聞いたり、自分が出したことばを自分で聞いたりしながら音を修正し、獲得していきます。
話し声が使われている場面は?
人間のコミュニケーション手段には、話し声の他にも、筆談や手話、身振り手振り、文字など様々なツールがあり、個人の事情に合わせて主に使うものは異なります。
しかし、話し声はその便利さから多くの場面で使われています。改めていくつかの場面を挙げてみましょう。
家族や身近な人との会話
家族や友人など身近な人との会話は、言うまでもなく、話し声でのコミュニケーションの場としては大きなものでしょう。
また、子どものことばの発達の面では、気持ちやことばのキャッチボールを身近な人と積み重ねていくことが非常に大切です。
会議や商談、同僚とのコミュニケーションで
仕事の場面でもコミュニケーションは大切です。交渉の場面では、相手のプレゼンテーションを聞いたり、伝えたことへの反応をみたりしながら、戦略を考えていくことでしょう。
視覚的な資料なども併用しながらも、音を聞くことが大切になる場面も多いものです。
電話
電話は相手の姿が見えず、まさに話し声という音だけでコミュニケーションを行うツールです。
電話は必要事項を伝えるだけの簡素なものだけではなく、遠方の人に悩みを相談したり、近況を報告しあったりといった便利なツールです。
メールやスマートフォンのアプリなどで文字だけでの連絡を行うことも多くなりましたが、相手の声を聞いて確認したいという人もいます。
また、電話カウンセリングなどでは、音に含まれる情報を敏感に感じ取りながら、会話をしていくことが求められることもあるでしょう。
学校の授業や、研修会など
映像やプリントなど視覚的な道具も併用されてはいるものの、話し声が占める授業や研修会は多いものです。
学校の授業のほか、社会に出てから資格取得のための講義や研修会を受けるということもあります。
病院や公共機関
病院や公共機関では、説明を聞いたり、不明点を尋ねたりする際には話し声が多く用いられます。
他にも順番を待っていて呼び出される際の、呼び出し音やメロディ、番号の読み上げなど、機械的な音が用いられていることも多いでしょう。
多くの人の話し声や足音など様々な雑音の中から、必要な情報を聞き取ることが必要です。
趣味
多くの人が様々な趣味を持っていますが、趣味の中でも楽器演奏や合唱、カラオケ、音楽鑑賞などでは音をたくさん聞いています。
また、同じ趣味を持つ人とのコミュニケーションや、講師の指導を聞く際には話し声が多く用いられています。
意外と聞いている生活音
人間の聴覚は、日常に当たり前のように存在している音をできるだけ気にしないように調整する力があります。
つまり、普段はあまり気になっていなくても、私たちの生活は話し声以外の多くの音に囲まれています。
風や雨など自然の音
住んでいる環境や天候によって異なるものの、風音や雨音、川の流れや波の音といった自然がつくりだす音がたくさんあります。
家事や家電製品の音
掃除機をかける音、料理をする音、洗濯や食器を洗う音など、家事にまつわる音も多様です。
また、現代の家庭には多くの家電製品があり、常に電源が入って動いているものも少なくありません。それらの家電製品ではモーターが動いているなど、何らかの音が常に起こっているものです。
テレビの音
多くの家庭にあるテレビからは、映像と共に話声や音楽などたくさんの音が流れます。人によっては、たとえ好みの番組がなくても電源を入れているということもあります。
音楽
クラシックに邦楽、洋楽、アニメソングに手遊び歌、インストゥルメンタルと、音楽の好みは様々です。中には自分で演奏をすることが楽しいという人もいるでしょう。
車や電車の音
車や電車など乗り物が発する音は、比較的意識しやすい音でしょう。しかし、最近では非常に静かな車も販売されていますし、自転車など、音だけでは近づいていることに気づきにくい乗り物もあります。
危険や緊急性を知らせる音
火事や地震を知らせる通知音や、運転中に消防車や救急車など緊急車両が近づく音や市町村からの放送など、普段とは異なる対応を求められる場面でも音が使われています。
まとめ
日常の中には、話し声や、話し声を使う場面のほか、無意識で聞いている音など様々な音があります。
こういった音に関わる場面では、聴覚障害のある人や、聴力の低下を感じている人が困っていたり、トラブルが起きやすかったりすることがあるということです。
もし、補聴器の購入を検討するのであれば、どういった場面で困っているかということを振り返っておくと機種を選ぶ際のヒントになるでしょう。
(本記事は、言語聴覚士が作成・監修しています。)
あわせて読みたい関連記事
この記事を監修した人

にじいろ補聴器 店長
言語聴覚士・認定補聴器技能者
千葉 星雄(ちば としお)
北海道出身・北海道大学 工学部 卒業
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 言語聴覚学科 卒業
言語聴覚士免許取得後、補聴器専門店と補聴器メーカーでの勤務を経てにじいろ補聴器を開業。